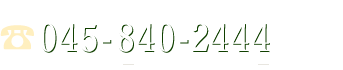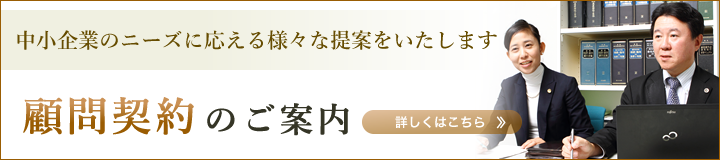遺言の無効を主張したい
平成29年6月15日号掲載
平成29年10月12日追記
亡くなった父が、全財産を私の兄に相続させるという内容の公正証書遺言を残していたことが分かりました。
しかし、父は生前、認知症を患っており、そのような遺言を行えたはずはありません。遺言の無効を主張したいのですが、可能でしょうか?
遺言能力とは
遺言を行うためには、遺言当時、遺言内容を理解して遺言の結果を弁識するに足りる能力(遺言能力)が必要です。遺言能力を欠いた状態で行われた遺言は、無効となります。
したがって、ご相談の件でも、お父様が遺言を行った当時、遺言能力を欠いた状態であったのであれば、その遺言は無効となります。
認知症と遺言能力
もっとも、遺言作成当時に認証を患っていたとしても、必ずしも遺言能力を欠いていたとなるわけではありません。認知症患者であっても、遺言当時、遺言内容を理解して遺言の結果を弁識できていれば、遺言能力は認められることになります。
遺言能力の判断基準
具体的にどのような要件がそろえば「遺言能力あり」と言えるかについては、必ずしも明確ではなく、裁判においても以下の事情等を総合的に考慮し、ケースバイケースで判断されます。
- (1)認知症や精神疾患がどの程度重症だったかのか、
- (2)遺言内容はシンプルなものか複雑なものか、
- (3)遺言内容は合理的か否か、当該遺言を残す動機の有無
遺言能力の判断材料を探す
ご相談のケースでは、まずは、お父様のかかり付け病院から診療記録を取り寄せて、認知症の重症度を確認することから始めてみてはいかがでしょうか。
認知症患者においては、多くの場合、病院で改訂長谷川式簡易知能評価スケール(長谷川式スケール)と呼ばれる検査を受けています。長谷川式スケールは、あくまでも簡易な振るい分け検査であり、この検査結果で直ちに認知症の重症度が判明するわけではありませんが、多くの裁判例でこの検査結果が遺言能力有無の判断の際に参考にされています。
長谷川式スケールは30点満点で採点されますが、裁判例においては点数が下がるにつれて遺言能力が否定される傾向がみられ、10点代であれば半々くらい、一桁であれば多くの場合には遺言能力が否定されています。
長谷川式スケール以外の精神疾患重症度の判断資料としては、次のようなものがあります。
- ・医師による診断書・意見書・鑑定書等
- ・頭部画像所見(CT検査・MRI検査等の画像)
- ・要介護認定のための調査結果
- ・介護サービス利用時の介護記録等
- ・本人が作成した書面(内容の合理性・筆跡の乱れ)
- ・遺言者の日常の様子を撮影したビデオ、録音テープなど
遺言の有効性の争い方
このご相談のケースでは、まずは当事者同士で話し合いを行うことになると思いますが、合意に至らない場合には、最終的には裁判手続きを利用せざるを得ません。
遺言の有効性を争う場合、原則としてまず家庭裁判所で調停を行う必要があります(調停前置主義)。調停で話し合いがつかない場合には、遺言無効確認訴訟を提起する必要があります。
弁護士に依頼するメリット
遺言の有効性を争う場合、上記のように多くの資料を収集し、多様な考慮要素を的確に判断したうえで当方の主張を組み立てる必要があります。
また、遺言の有効性を争う際、多くのケースでは、遺言が有効と判断された場合に備えて、遺留分減殺請求も併せて主張する必要があります。
弁護士に依頼することで方針の決定、証拠収集についてアドバイスすることができますし、なにより裁判のための書面作成、裁判手続きの対応を本人に代わって進めることができます。
遺言無効のことで問題が発生したら、問題が大きくなる前に、すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。
遺言書の無効については、遺言書に不服があるときの裁判所の手続(調停、訴訟)も併せてご覧ください。
-
2024/06/06お知らせ
-
2025/01/01お知らせ
-
2024/12/09お知らせ
-
2024/12/05解決事例
-
2024/10/09お知らせ
-
2024/09/12解決事例
-
2024/09/12解決事例
-
2024/09/12お知らせ
-
2024/09/12解決事例
-
2024/07/19お知らせ