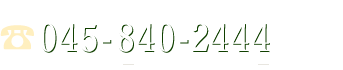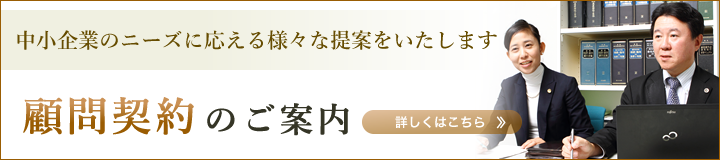不動産の生前贈与と特別受益
相続人の中に、被相続人から不動産の生前贈与を受けていた場合、特別受益(民法903条1項)にあたるかが問題となります。
生計の資本としての贈与だった場合は、その生前贈与の分は、遺産に戻して計算されます(「特別受益の持ち戻し」と言います)。
特別受益の計算方法
例えば、次のような事例を想定します。
- 被相続人:母親
- 相続人:長男と次男の2名
- 遺産総額:5000万円
- 生前贈与:長男が、母親から2000万円の不動産の贈与を受けていた。
この場合、不動産は遺産の金額に戻して計算されます(5000万円+2000万円=7000万円)
長男と次男が遺産から取得できる金額は次のようになります。
- 長男:7000万円÷2-2000万円=1500万円
- 次男:7000万円÷2=3500万円
生前贈与の分を考慮すると、長男と次男は3500万円ずつを取得することになり、相続人同士の公平が図られることになります。
家族それぞれに不動産を贈与していた場合
例えば、長男も次男も生前に不動産の贈与を受けていた場合は、どちらも戻して計算されます。
不動産の評価の時点
不動産は、原則として、相続発生時(つまり母親死亡時)の時価で計算されます。
持ち戻しが免除される場合
被相続人が、生前贈与を持ち戻すことを免除する意思であったことが推認される場合、持ち戻しが免除されることがあります。
例えば、本事例では、長男が病気を抱えており、自分では家を買ったり賃料を払うことができないような事情があった場合は、持ち戻し免除の意思があったと推認される場合もあります。
ただ、この持ち戻し免除は、簡単には認められません。
当事務所の最新トピックス・解決事例は、下記をご覧下さい。
-
2025/04/14お知らせ
-
2025/04/08お知らせ
-
2025/01/01お知らせ
-
2024/12/09お知らせ
-
2024/12/05解決事例
-
2024/10/09お知らせ
-
2024/09/12解決事例
-
2024/09/12解決事例
-
2024/09/12お知らせ
-
2024/09/12解決事例
主な取り扱い分野